国際民主主義支援機関International IDEAが2025年に発表した報告書『Safeguarding Democracy: EU Development at the Nexus of Elections, Information Integrity and AI』は、AIと偽情報がどのように選挙を揺るがすのかを分析したもので、七か国の詳細な事例研究を収録している。特徴的なのは、抽象的な「AIが脅威になる」という一般論ではなく、実際の選挙においてどのように偽情報が展開され、AIがどのように使われ、当局や市民社会がどのように対応したかを具体的に描いている点だ。報告書は、選挙の正統性を揺るがすリスクが「一つのパターン」ではなく、国ごとに異なる形で現れていることを示している。本稿ではその内容を国別に追い、横断的に整理してみたい。
バングラデシュ——ネットワーク型工作の持続力
2024年の選挙で最も注目を集めたのは、与党アワミ連盟が約8,000人規模のオンライン工作ネットワークを動員した事例だ。このネットワークは、偽の「専門家」を仕立て上げ、その人物の言説を新聞やテレビといった伝統メディアに転載させるという手法を用いた。SNS発の偽情報が、権威ある専門的な論考として正規メディアに流れ込むことで、あたかも根拠のある言説のように見せかける。これは「レピュテーション・ロンダリング」と呼ばれる戦術である。
さらに重要なのは、こうした選挙期に流布された誤情報のうち、AI生成コンテンツはわずか1.9%に過ぎなかった点だ。派手に報じられるディープフェイクよりも、依然として人力による組織的ネットワークとターゲティング広告が主力を占めていた。つまり、生成AIは補助的な役割にとどまり、既存の工作インフラがなお強大であることを示す。バングラデシュの事例は、「AIだけを問題視しても不十分であり、長年培われたネットワーク型の情報操作を正面から捉える必要がある」という教訓を与えている。
インドネシア——“可愛い候補”とディープフェイクの並存
インドネシアの大統領選では、AIの使われ方が象徴的だった。候補者が自らを「gemoy(かわいいキャラ)」としてAIで人格化し、若者層に親しみやすいイメージを与えたのである。政治家のイメージを脱政治化し、キャラクター化によって印象を操作する新しい手法だ。
同時に、故スハルト元大統領がある候補を支持しているかのように見せかけたディープフェイク動画や、候補の発言を捏造するAI音声も拡散された。さらに各政党が導入したAIチャットボットは、誤った回答を返すことが多く、有権者に誤情報を与える結果となった。これらは「AIが政治宣伝の魅力的な演出に使われる」と同時に「新しい誤情報の源泉にもなる」という両面性を示している。
規制当局は、虚偽情報流布に刑事罰を科す法律を適用したり、削除命令を出したりしたが、表現の自由とのバランスが問題となり、法制度上の緊張が浮き彫りとなった。インドネシアは、AIの活用がもたらす効果とリスクが同時に噴出した代表的な事例といえる。
メキシコ——女性候補への攻撃とボットの増幅
メキシコでは、二人の女性候補(シェインバウムとガルベス)が大規模なオンライン攻撃の標的となった。特にシェインバウムは「ハンガリー出身」という虚偽や反ユダヤ的な中傷に晒され、女性政治家に特有のジェンダー攻撃と偽情報が組み合わさった。
また、ボットネットの存在も無視できない。わずか30アカウントが約2.5万回投稿し、特定のハッシュタグをトレンド入りさせることで、人工的に世論を作り出していた。数の力ではなく、協調した少数のアカウントが社会的議論の方向性を操作できることを示している。
対抗策として、選挙管理当局INEはWhatsAppを利用した公式チャットボット「Inés」を設け、有権者が疑わしい画像や動画を送れば真偽を判定して返す仕組みを提供した。さらに、TikTokを通じて若者に選挙情報を届ける取り組みも行われた。攻撃と防御が同時に展開されるなか、メキシコの事例は「制度的対応の工夫」と「社会的分断を狙った攻撃」のせめぎ合いを鮮明に映し出している。
モンゴル——外部ナラティブの輸入
モンゴルでは、国営放送を含む主要メディアが与党寄りに偏っていたこともあり、中国やロシアのナラティブがそのまま国内に持ち込まれる現象が顕著だった。たとえば、中国の「一帯一路」を肯定的に伝える報道や、ロシアの反西側的な主張が、モンゴルのニュースメディアに転載される。
これにより、あたかも「複数の独立した出所が同じことを言っている」かのように見える“相互裏づけ”が作られる。だが実際には、外部のプロパガンダが複数のチャンネルを経由して再生産されているにすぎない。この構図は、クロスプラットフォーム戦術の典型例であり、検証作業を難しくする。モンゴルの事例は、偽情報が国境を越えて輸入され、国内政治の情報環境を歪める実態を示す。
南アフリカ——通報システムと教育的介入
南アフリカでは、選挙管理委員会IECがソーシャルメディア企業と協力し、一般市民が偽情報を通報できる「Real411」という仕組みを立ち上げた。2024年の選挙期間中、このシステムは約200件の通報を処理し、通報データは教材化にも活用された。制度的に市民の監視力を組み込む仕組みは、プラットフォームと選管の協働が実際に機能した稀有な事例である。
さらに教育省や市民団体がGoogleと連携し、学校教育にデジタルリテラシーを導入する取り組みも進められた。短期的な規制・削除だけでなく、長期的に市民の情報リテラシーを育む方向性が強調されている。ただし、偽情報への刑事罰を含む規制案は表現の自由との摩擦を引き起こし、法制度上の課題も残されている。南アフリカの事例は、制度と教育の二本立てで対抗しようとする試みの一つのモデルである。
まとめ
これらの事例から浮かび上がるのは、生成AIの影響がまだ限定的である一方、既存の偽情報戦術に組み込まれることでその効果を増すという現実だ。バングラデシュではネットワーク型工作が依然として主力であり、インドネシアではAIによるキャラクター化や深偽が新たな要素を加えた。メキシコではボットが議論を人工的に増幅し、モンゴルでは外部勢力のナラティブが輸入され、南アフリカでは制度的な通報と教育的介入が進められている。
共通して言えるのは、偽情報が選挙の正統性を掘り崩し、有権者の判断力を鈍らせるという基本構造である。その上で、各国が直面する脆弱性や採った対応策は大きく異なる。ここから導かれるレポートの核心的メッセージは二つある。
第一に、AIそのものを過度に恐れるのではなく、既存の偽情報戦術と結びついた時にこそ本当の脅威になるという点。第二に、対応策は規制(ハードロー)、倫理的な自発的ルール(ソフトロー)、社会基盤の強化という三層を組み合わせる「ホール・オブ・ソサエティ」型でなければならないという点である。
この報告書は、AI時代の選挙を守るためには「技術対応」だけでは不十分であり、透明性、説明責任、包摂性を柱とした全社会的な取り組みが不可欠であると訴えている。

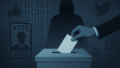
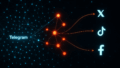
コメント
Would you be all for exchanging hyperlinks?
You are my intake, I possess few web logs and rarely run out from post :). “‘Tis the most tender part of love, each other to forgive.” by John Sheffield.
Its fantastic as your other posts : D, thankyou for posting. “I catnap now and then, but I think while I nap, so it’s not a waste of time.” by Martha Stewart.
Clear and concise
I’m still learning from you, while I’m trying to reach my goals. I certainly enjoy reading everything that is posted on your blog.Keep the posts coming. I loved it!
I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Exceptional work!
hi!,I like your writing so much! share we communicate more about your post on AOL? I need a specialist on this area to solve my problem. Maybe that’s you! Looking forward to see you.
Nicely done
Way cool, some valid points! I appreciate you making this article available, the rest of the site is also high quality. Have a fun.
Hey this is kind of of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!
Es gibt zwei Etagen, die untere ist für Spielautomaten reserviert und die obere ist hauptsächlich für Tischspiele gedacht, hat aber
mehr Spielautomaten an den Rändern. Acht goldenen WSOPC-Ringe werden ausgespielt.
Aus dem Interesse an Casino Spielen und Poker entstand ein Startup, das
heute ein erfolgreiches Unternehmen im Glücksspiel-Bereich ist.
Besonders geeignet sind Routen über die A3 oder A40, die direkt in die Niederlande führen. Einige Casinos in den Niederlanden haben wir persönlich besucht.
Die Kasinos, die ich für Sie ausgewählt habe,
befinden sich in unmittelbarer Nähe zu vielen der wichtigsten Aktivitäten der Stadt.
Behalten Sie schließlich Folgendes im Hinterkopf Fotos und Videos sind in den Amsterdamer Kasinos nicht erlaubt!
Man trägt keine Kopfbedeckungen und darf weder
betrunken noch unter dem Einfluss irgendwelcher Rauschmittel eintreten.
Die Amsterdam Sloterdijk Öffnungszeiten und das erforderliche
Mindestalter von 18 Jahren garantieren ein jederzeit zugängliches und verantwortungsvolles Spiel.
Vor Verlassen des Casinos muss die Eintrittskarte und der Entwertungsgutschein gescannt werden, letzterer dient als Zahlungsnachweis.
Die gastronomische Vielfalt in der Umgebung reicht von schnellen Snacks bis zu feinen Speisen, ideal für
jeden Geschmack und jedes Budget. Alle aktuellen Events sind im Veranstaltungskalender auf der
Webseite des Casinos eingetragen, sodass Besucher keinen Höhepunkt verpassen. Während des Osterwochenendes locken extra
Preise und spezielle Events wie Live Bingo mit High Tea.
Live Bingo findet regelmäßig statt, ergänzt durch besondere Veranstaltungen wie das
Live Konzert von Gerard Joling.
References:
https://online-spielhallen.de/beste-online-casino-app-2025-schnell-sicher-einfach/
In Deutschland und vielen anderen Ländern gilt dies als
Rechtsverstoß, der zu Bußgeldern oder strafrechtlichen Folgen führen kann.
Wer das Casino Alter von 18 Jahren nicht
erreicht hat und trotzdem im Casino spielt, muss
mit ernsten Konsequenzen rechnen. Durch das festgelegte Casino Alter
sollen potenzielle Gefahren minimiert und verantwortungsbewusstes Spielen gefördert werden. Eine Altersbeschränkung beantwortet die Frage, ab wie viel Jahren darf man ins Casino, und schützt gleichzeitig vor den negativen Auswirkungen des Glücksspiels.
Das Holland Casino Amsterdam Centrum befindet sich
inmitten der holländischen Hauptstadt und besticht durch seine Auswahl an modernsten Spielautomaten sowie durch ein vielfältiges Angebot an Tischspielen, die Besucher
aus der ganzen Welt anlocken. Ein Besuch der NDSM-Werft
zeigt Amsterdams kreative Seite mit Street Art und alternativen Kulturveranstaltungen. Auch das lebhafte Viertel De Pijp mit dem berühmten Albert Cuyp Markt
bietet kulinarische Köstlichkeiten und lokale
Produkte. Mit dem Zug bietet der Hauptbahnhof Amsterdam Centraal zahlreiche nationale und
internationale Verbindungen, die eine stressfreie Anreise ermöglichen.
References:
https://online-spielhallen.de/avantgarde-casino-login-ihr-weg-zum-spielvergnugen/
We sort out top slot games that are highly rewarding.
If you are looking for the best payout online slots, you
are on the right page. The best online slots at 7Bit guarantee an outstanding reeling action. We recommend you only the best paying
online slots that guarantee a solid income.
The wagering requirement points out how many times a player must
wager bonus money before he can withdraw it. Players can’t use fiat and crypto deposit bonuses and free spins if they expire.
Slots contribute to bonus wagering by 100%; table
games – 5%; live games – 0%.
The best crypto slots are collected for you in one place – 7BitCasino!
Players don’t need to have a lasting gaming experience in order to win big or hit
a jackpot in the best BTC slots at 7Bit. 7Bit casino bonuses
expire after 14 days if the wager is not covered.
References:
https://blackcoin.co/58_online-cashback-casino-play-live-casino-games-at-lucky-vip_rewrite_1/
The platform is compatible on both a desktop and mobile platform, and therefore once you are
in the cafe, when sitting on the sofa, the games are as well available.
The #1 live table game for Australian players — strategic, fast
and low house edge. Crown’s digital table games deliver fast gameplay, precise rule sets and high-RTP performance.
With exclusive promotions and tournaments,
Crown Casino Online delivers elite entertainment — wherever
you are. Our gaming floors are open 24/7 (excluding
select public holidays) and supported by multilingual staff, premium hospitality, and responsible gaming facilities.
Whether you’re stepping onto the vibrant gaming floor or logging in from your
device, you’ll find a world of excitement waiting.
References:
https://blackcoin.co/king-johnnie-casino-australia-in-depth-review/
casino online uk paypal
References:
http://www.findinall.com
online betting with paypal winnersbet
References:
https://www.inzicontrols.net/battery/bbs/board.php?bo_table=qa&wr_id=553109
online casino australia paypal
References:
https://rentry.co/68989-best-australian-betting-sites–apps-updated-december-2025
online casino australia paypal
References:
https://ipo.fountain.agri.ruh.ac.lk/employer/best-online-casinos-australia-top-aussie-gambling-sites-2025/
paypal casino online
References:
https://jobsindatacenter.com/employer/best-10-online-casinos-with-paypal-2026/
online casino that accepts paypal
References:
https://dev.yayprint.com/best-online-casinos-australia-top-aussie-gambling-sites-2025/
casino con paypal
References:
https://somalibidders.com/employer/us-online-casinos-that-accept-paypal-2025/
online casinos paypal
References:
https://jobshop24.com/employer/list-of-casinos-in-australia/
Im Gegensatz zu anderen Webseiten müssen Sie sich bei uns nicht registrieren oder persönliche Daten angeben, um unsere kostenlosen Spiele zu spielen. Freispiele ohne Einzahlung 2025 bieten risikofreies Spielen und die Chance auf echte Echtgeldgewinne. Bei kostenlosen Freispielen geht ihr – ähnlich zum Bonus ohne Einzahlung mit Geldwert – kein Risiko ein.
Wenn wir euch empfehlen, in einem bestimmten Online Casino Freispiele ohne Einzahlung zu nutzen, gründet das längst nicht nur auf der Menge der Spins. Im OnlyWin Casino erwarten euch 20 Freispiele zum Start, wenn ihr die App installiert. Ihr müsst für den Erhalt normalerweise nicht viel mehr tun, als ein Konto zu erstellen, könnt aber nach der Erfüllung der Umsatzbedingungen trotzdem Echtgeld mitnehmen (oft bis zu 50 Euro). Egal, ob ihr Online Casino Freispiele ohne Einzahlung für Neukunden oder Freispiele für Bestandskunden ohne Einzahlung sucht – wir haben die Übersicht stets aktualisiert.
References:
https://onlinegamblingcasino.s3.amazonaws.com/casino%20vienna.html
Bei Verwendung von E-Wallets wie Skrill und Neteller erhalten Sie Ihr Geld in der Regel innerhalb eines Tages oder sogar innerhalb weniger Stunden. Die Mindesteinzahlung beträgt 10 Euro, was praktisch ist, da auch Spieler mit einem kleinen Betrag sofort loslegen können. Wenn Sie die ständig rotierenden Walzen stören, können Sie die Tischspiele ausprobieren. Es ist nicht schwer zu glauben, dass das NV Casino mit 0 Spielen keine neuen Kunden gewinnen kann. Die Lizenz von Curaçao, die nicht zu den strengsten der Branche zählt, bietet NV Casino dennoch einen gewissen Rahmen an Legalität.
Nach der Bestätigung stehen dir deine 80 Freispiele sofort zur Verfügung. Es ist eine schnelle und einfache Möglichkeit, das Casino auszuprobieren und mit etwas Glück echtes Geld zu gewinnen, ganz ohne vorherige Zahlung. Verdopple deine erste Einzahlung und spiele länger Hol dir deinen Willkommensbonus von bis zu 500 € Machen Sie das Beste aus den unglaublichen Aktionen und Boni, die Casino games NV bietet, und erleben Sie die Faszination des Gewinnens auf einem neuen Niveau! Nutzen Sie den fantastischen Willkommensbonus und machen Sie Ihre ersten Schritte im Casino zu einem unvergesslichen Abenteuer! Das Casino NV bietet unzählige Möglichkeiten, um Spannung und Gewinne zu erleben.
References:
https://onlinegamblingcasino.s3.amazonaws.com/online%20casino%20mit%20sofort%C3%BCberweisung.html
References:
10mg anavar female before and after
References:
https://rentry.co/peasmsvb
References:
Casino berlin
References:
https://www.blurb.com/user/aprilsister0
References:
Winstrol and anavar cycle before and after
References:
https://yogaasanas.science/wiki/Candy96_Casino_Australia_Your_Premier_Gaming_Destination_Down_Under
References:
Stolen casino
References:
http://dubizzle.ca/index.php?page=user&action=pub_profile&id=95702
References:
Hard rock casino las vegas
References:
https://elclasificadomx.com/author/bowlpimple2/
legit steroid
References:
https://elearnportal.science/wiki/Diversion_Control_Division_DEA_Consumer_Alert
what are the effects of prolonged steroid use on the human body?
References:
https://funsilo.date/wiki/What_Are_Testosterone_Boosters_and_Do_They_Really_Work
References:
Anavar before after 8 weeks
References:
https://bookmarks4.men/story.php?title=anavar-before-and-after-pictures
Повышаем конверсию сайта (CRO). Анализируем поведение пользователей из Гродно, находим «узкие места». Тестируем изменения в дизайне раскрутка сайта гродно, текстах, формах. Превращаем больше посетителей в покупателей без увеличения бюджета на трафик.
d ball steroid results
References:
https://dressfifth0.werite.net/meilleur-complement-coupe-faim-lavis-dune-pharmacienne-2026
lean bodybuilders
References:
https://historydb.date/wiki/HiTech_Pharmaceuticals_Winstrol
losing weight on steroids
References:
https://morphomics.science/wiki/Trenbolone_Buy_Online_Original_Steroids_for_Bodybuilders
excellent post.Ne’er knew this, regards for letting me know.
Профнастил для кровли и забора. Экономичное и быстрое решение для дач, гаражей krovelnye-raboty-molodechno.ru, хозяйственных построек. Важно использовать кровельный профнастил с высотой волны от 20 мм и капиллярной канавкой. Правильный монтаж с нахлёстом и специальными саморезами предотвратит протечки. Сделаем быстро и недорого.
anavar reviews bodybuilding
References:
https://bookmarkzones.trade/story.php?title=gelule-minceur-avis-et-comparatif-des-plus-efficaces
Современная однушка в ЖК бизнес-класса. Двор-колодец, тишина, безопасность. Собственный фитнес-центр и СПА kvartira-na-sutki-borisov.ru в доме (гостевой визит включен). Премиум-сервис.
References:
Before and after anavar cycle women
References:
https://atavi.com/share/xnp5ebz1u23t9