近年の偽情報研究では、単にコンテンツの真偽を問題にするだけでは不十分だとされる。EU対外行動庁が定義したFIMI(Foreign Information Manipulation and Interference)は「違法か否かにかかわらず、協調的に行われる操作的行為」を指す。重要なのは、単発の嘘や誤情報ではなく、偽サイトの立ち上げ、AI生成物の投入、ボットによる拡散、なりすましアカウントの利用といった一連の“行動パターン”全体が脅威として位置づけられる点だ。
カナダのMIGS(Montreal Institute for Global Security)が2025年9月に公開した報告書『WIRED FOR WAR』は、この行動重視の視点を基盤に、生成AIやSNSが認知戦をどう変質させているかを具体的に描き出す。
技術が変えたコスト構造
報告書が強調するのは、量・速度・不可視化の三要素が一度に拡大したことだ。
- 量:AIで記事や画像、音声、動画を自動生成することで、数千件規模の偽情報を一度に投入できる。
- 速度:翻訳や口調模倣が容易になり、多言語でほぼ同時に展開できる。
- 不可視化:情報洗浄、匿名アカウント、ボット群を使い、出所を隠したまま流通させられる。
米司法省が2024年に摘発した事例は象徴的だ。ロシアのRTが関与するAI駆動ボットファームが数千の偽アカウントを運用し、米国内外で分断を煽っていた。国家機関と外郭メディアが結びつき、AIで人間らしい“市民”を大量生産する構造が明らかになった。
事例1:Matryoshka / Operation Overload — コメント欄を戦場に
2023年以降、欧州を中心に観測された「Matryoshka(Operation Overload)」は、もっとも注目すべき作戦の一つだ。流れはこうだ。
まずロシア語圏のTelegramで偽情報や合成メディアを作成・公開。そこからXやBluesky、TikTokに持ち込む。特徴的なのはXの返信欄を狙った戦術で、ファクトチェッカーやメディアの投稿の下に数千件の偽コンテンツを連投し、検証リソースを過負荷に追い込む。報告書は約1.1万のアカウントがこの増幅ネットワークに関与していたと指摘する。
素材も精巧だ。欧米の著名人になりすました動画や、AIで生成した音声クローンを含み、一見本物らしく見える。さらに親露系インフルエンサーや“偽ジャーナリスト”が再投稿して正規流通に混ぜ込む。こうして「Telegram起点 → X返信埋め → インフルエンサー増幅」という分業構造が成立した。
事例2:ルーマニア大統領選 — アルゴリズムが民主主義に食い込む
2024年のルーマニア大統領選では、FIMIとプラットフォームの統治不全が重なり、投票が無効化される異常事態となった。
欧州委員会はTikTokが政治広告や推薦アルゴリズムの透明性規則に違反した疑いで調査を開始。調査団体は、アルゴリズムが中立的なユーザーに極右コンテンツを過剰に推奨していたと指摘した。さらに再選挙時には、Telegram創業者が全国通知を送るという異例の出来事が起き、プラットフォームそのものが政治過程に介入した形になった。
この事例は、単なるコンテンツ削除ではなく、推薦アルゴリズムの設計や通知機能の統治が民主主義の正統性に直結することを示した。
事例3:カナダ総選挙 — TikTok発ディープフェイクと「説明動画」の罠
2025年のカナダ総選挙では、首相が規制を発表する偽動画がTikTokで拡散した。ファクトチェッカーはAI生成と判定し、否定報道も出た。だが流通は止まらなかった。
次の段階では、「解説動画」やインフルエンサーのコメントとしてXやFacebookに再拡散された。偽情報は否定されるどころか、「話題」として息を吹き返した。さらに偽CBCサイトや投資詐欺ページが抱き合わせで利用され、政治的混乱と経済詐欺が結びつく複合的作戦となった。
このパターンが示すのは、一次ソースの削除だけでは足りないという現実だ。誤情報は「解説化」「模倣サイト」「インフルエンサーの再利用」によって延命され、否定報道すら燃料となり得る。
事例4:AIボットファーム — 国家と外郭の結節点
RTと連携したAI駆動のボットファームは、生成AIで作られた記事やコメントを、偽アカウント群を通じて各国に流し込んでいた。これらは単なる自動化ではなく、ターゲット地域の言語や文化に合わせて最適化されていた。AI翻訳とローカライズの活用により、外部勢力が現地発信者のように振る舞うことが可能になった。
この構造は、国家と非国家の境界を曖昧にし、プロパガンダと詐欺・犯罪を同じインフラで動かすことを可能にしている。
認知戦としての位置づけ
報告書は、これらの事例を単なる偽情報ではなく「認知戦」として捉える。狙いは情報の内容ではなく、市民の信頼・制度の正統性・意思決定プロセスそのものだ。
生成AIやアルゴリズムは、注意や感情に直接作用する“説得技術”となりつつある。広さ(拡散)と深さ(個別影響)が同時に強化されることが、従来型プロパガンダとは異なる危険性だ。
防御の方向性
報告書が導く結論は二層に整理できる。
- プラットフォーム統治の強化
- 推薦アルゴリズムの外部監査
- 政治広告・通知機能の透明化
- 半公開空間(Telegramなど)への国際的対応
- 行動ベースの検知
- DISARMやMITRE ATT&CKのような行動知識ベースの活用
- 初出点、拡散経路、アカウント群の再利用といったメタデータ分析
- 大量同時発生や協調の兆候を検知する仕組みの整備
単発のコンテンツ削除ではなく、行動パターンを早期に察知する仕組みがなければ防御は成り立たない。
結論:行動を読むことが防御の第一歩
『WIRED FOR WAR』が提示するのは、偽情報を「誰が」「どの技術で」「どの経路を使い」「どのような行動パターンで」流すかという包括的な視点だ。
Matryoshkaの返信欄埋め、ルーマニア選挙でのアルゴリズム偏向、カナダ選挙でのディープフェイクの再利用、RTとAIボットファームの連携。これらは別々の出来事に見えても、裏では「低コストで試し、成功パターンを繰り返す」という同じ設計思想が働いている。
だからこそ、行動を読み解き、行動に介入する。これが、民主主義が耐性を保つための現実的な道筋だと報告書は強調している。

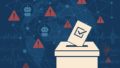
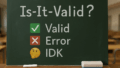
コメント
Casinos nutzen Boni ohne Einzahlung als Marketinginstrument, um neue Spieler zu gewinnen und sie zu einer Registrierung zu motivieren. Freispiele
haben im Normalfall bessere Bedingungen wenn es um die Wettanforderung geht,
aber meistens sind Freispiele nur für einen kurzen Zeitraum umsetzbar.
Wenn Du einen Online Casino Bonus ohne Einzahlung bekommst, bedeutet das,
dass Du auch die Chance hast, Geld zu gewinnen, ohne das
Risiko, Dein eigenes Geld zu verlieren.
Bei einem normalen Casino Bonus ist es in der Regel so, dass
man eine Echtgeldeinzahlung tätigen muss, bei der man dann einen entsprechenden Code angibt,
um überhaupt für den Bonus zugelassen zu werden. Diese Boni ermöglichen es dir, sofort nach der
Registrierung echtes Geld oder Freispiele zu erhalten – ohne eigenes Geld einzuzahlen.
Bestimmte Casino-Spiele können mit solchen Angeboten immer risikofrei und unverbindlich
ausprobiert werden, während man sich gegebenenfalls ein wenig Echtgeld erspielt.
Zu den in Deutschland gängigsten Casino-Zahlungsmethoden für Echtgeld-Auszahlungen zählen beispielsweise Banküberweisungen oder E-Wallets.
Allerdings erfordert eine Auszahlung der Echtgeld-Gewinne, wie bereits erwähnt,
eine Erfüllung eines bestimmten Mindestumsatzes.
Auf diese Weise möchten sie mehr Kunden für
ihre Glücksspiel-App gewinnen.
References:
https://online-spielhallen.de/wunderino-casino-login-ihr-tor-zu-spannenden-spielen/
We support Australian players with casino-related issues and pass
formal complaints to the Australian Communications and Media
Authority when applicable. Yes, new players can enjoy a very favourable
casino bonus at Dolly Casino. The persistently expanding gaming selections have entitled the casino for the
level of superiority in offering the finest collection of games that
you will definitely like.
Register today, claim your welcome bonus, and discover why this platform consistently ranks among
Australia’s preferred online gaming destinations.
Regular players access VIP tiers with cashback, faster withdrawals, and exclusive
tournament invitations. Only progressive jackpot pokies and live
dealer games require real-money play. PayID payments arrive faster than traditional banking—deposits land instantly, withdrawals process within 24 hours for verified accounts.
PayID withdrawals land in your account within 1-3 hours for verified players—exceptional speed in an industry where 2-5 day waits remain common. This
hands-on assistance makes the onboarding experience remarkably smooth, even for first-time online casino users.
References:
https://blackcoin.co/ecarte-poker/
The translated text is re-inserted into your document, preserving the original layout.
Upload your document and we’ll instantly translate
it for you while preserving its delicate layout. Simply input the English words or text, select your desired target language, and get
the online translation instantly. Then, select the source
and target languages you want to translate to.
Our services are based on subscription plans that can be adjusted
according to your needs and preferences (access to a Premium Translator, additional setup, personal Account Manager,
etc.). Once you have passed the assessment, you’ll be
able to become a regular translator and translate blog articles, social media posts,
Zendesk tickets, and more into your account.
If you are a qualified language translator, we’ll be happy to have you on our translator team.
You can easily access Translate.com’s powerful platform to translate your website content or a ticket in a no-hassle environment.
The entire workflow is fully automated with an intuitive API, ensuring timely delivery and content adaptation.
The train from Sydney to Canberra will take approximately 4 hours.
Explore the most current information on trains from Sydney to Canberra Sydney AirportInternational Terminal T1,Bay 9, bus & coach bays This service stops daily
at the Sydney International Airport (T1).
Please check our booking page for service availability.
References:
https://blackcoin.co/clams-casino-in-depth-review/
online casino mit paypal
References:
http://www.ptshop.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=1332
casino sites that accept paypal
References:
http://carecall.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=2092656
online betting with paypal winnersbet
References:
https://chefstaffingsolutions.com/employer/top-online-casinos-for-real-money/
online casinos paypal
References:
https://carrefourtalents.com/employeur/best-online-casinos-australia-2025-find-top-aussie-casino/
casino sites that accept paypal
References:
https://jobsharmony.com/companies/best-real-money-online-gambling-sites-in-2025/
us online casinos that accept paypal
References:
https://talentformation.net/employer/best-online-casinos-that-accept-paypal-in-2025/
References:
Anavar steroids before and after
References:
https://securityholes.science/wiki/Privacy_Policy
References:
Anavar results before after female
References:
https://notes.io/eyNB4
References:
Casino arizona talking stick
References:
https://doodleordie.com/profile/burnairbus4
what happens when you stop using steroids
References:
https://fitch-gomez.blogbright.net/the-right-status-of-dianabol-in-usa
prolabs steroids
References:
https://www.pathofthesage.com/members/puppyenergy41/activity/740210/
how long is a steroid cycle
References:
https://bookmarking.stream/story.php?title=testosterone-cream-2
winstrol pills side effects
References:
https://bom.so/mFAjn5
References:
Take anavar before or after workout
References:
https://hedgedoc.eclair.ec-lyon.fr/s/UuW6u6jDg
prednisone alternatives
References:
https://lovebookmark.date/story.php?title=%C2%BFentrenar-con-pesas-pesadas-aumenta-la-testosterona-conoce-la-conexion-de-los-musculos-y-el-cerebro-salud-la
References:
Lady anavar before and after
References:
https://skitterphoto.com/photographers/2135177/saunders-mann
supplement closest to steroids
References:
https://bookmarkingworld.review/story.php?title=comment-payer-sur-internet-en-toute-securite-